ブランドデザインとは?
簡単にいうとブランディング全体を
デザインすること!
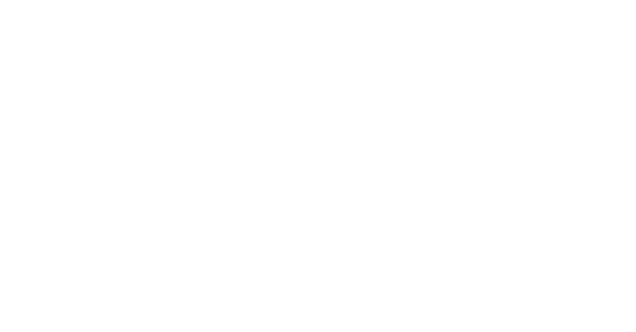
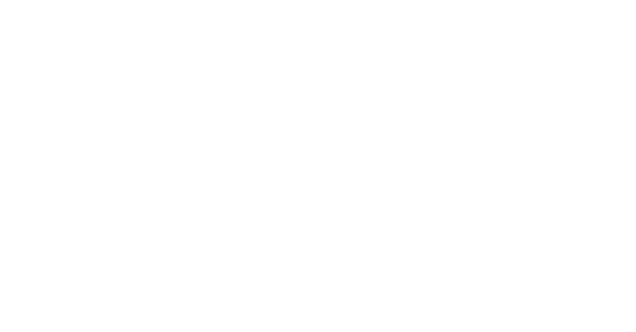
今回のテーマは「ブランドデザイン」についてです。
ブランドデザインとは文字通りブランドをデザインすることなのですが、具体的にどのようなことなのかを説明していきます。わかりやすく説明するために「ブランド」と「デザイン」の2つに分けて考えていきます。
「ブランド」については、以前の記事で
〜ブランドの定義〜
生活者が商品やサービスの「意味ある差」に共感し、
ファンになっている状態
と定義し詳しく説明をしていますので、今回は後半の「デザイン」を中心に「ブランドデザイン」を深掘りしていきます。

一般的にデザインと言うと、形状や絵柄などのビジュアルデザインをイメージする方も多いと思いますが、この「デザイン」にはいろいろな意味が含まれます。
ブランドデザインの「デザイン」の範囲は広義の意味で使用され、上記の「ビジュアルデザイン」はもちろんですが、「課題解決」や「設計」などの意味を含んでいます。
ブランドデザインには、実際どのようなデザインがあるのかを例を挙げ紹介していきます。
ブランドデザインの例)
ブランド全体のデザイン(ブランド戦略設計)
ブランドのコンテクストデザイン(文脈設計)
ブランドジャーニーマップデザイン(文脈設計)
ブランド価値のデザイン(ビジュアルデザイン)
ブランド接点のデザイン(コミュニケーション設計)
ブランド体験のデザイン(UX設計)
ブランドPDCAのデザイン
では、ブランドデザインの上記の内容を一つづつ簡単に説明していきます。
ブランディングの根幹の考え方や仕組みを考えることを「ブランド戦略設計」と言います。
まず自社、競合他社、生活者(顧客)の分析(3C分析)を行います。自社や競合他社分析を中心に商品やサービスの「ブランド価値」を見つけ出していきます。また、生活者分析などにより目指すべきブランドターゲットを設定し、ブランドペルソナを構築します。
そのブランドペルソナに対しコンタクトポイントを設計し、適切なタイミングでブランドの認知・理解・共感などを試みます。
その後、接触回数、頻度を高め生活者にブランドに対する良いイメージを抱いてもらい、ファン化へとつなげていけるよう戦略策定していきます。
コンテクストとは、日本語に訳すと「文脈」という意味になります。企業と生活者は立ち位置や求めるもの、経験や知識が異なっています。そこで、生活者にブランドを認知、理解してもらうために文脈、つまり伝える言葉だけではなく経験などすべてを合わせる必要がでてきます。この文脈を設計することをコンテクストデザインと言います。
ターゲットにブランドを認知してもらい最終的にファン化するまでの心理変容の道のりを設計することです。
商品やサービスなどにより心理変容の区分は変わりますが、大きく下記のような区分で生活者の心理がどの様に変化していくかを可視化していきます。

ビジュアルデザインは一般的に使用されている「デザイン」にあたり、ロゴ、パッケージ、サイト、写真や動画などブランドに関わる視覚的なデザインを指します。
人間の五感の中では受け取れる情報量が多い視覚が、ブランドイメージを生活者に残すことには向いています。ブランド価値をビジュアライズすることで、他との差別化を生活者にわかりやすく伝えることができ、共通イメージを使用することで想起率を高めていくことが可能になります。
ブランドイメージやブランドのトンマナなどの管理のために、ブランドブックやガイドラインなどを用いることも重要です。
店舗や店員、商品などのオフラインだけではなく、WebサイトやSNS等のオンラインも含め、生活者がブランドと接触するポイントでのコミュニケーションを設計することです。各接点の特徴(向き不向き)を把握した設計を行うのはもちろん、ブランドジャーニーマップなどで見える化された生活者の心理も考慮に入れることが重要になります。
オンライン・オフラインでブランド価値をどのように体験させるのかを設計することです。
商品パッケージでのワクワク感の醸成や簡単でわかりやすい操作方法など、すべての生活者満足体験(UX)を設計していきます。
また、イベントなどリアルに体験ができるものやオンライン動画やVR等での疑似体験などの設計も含みます。
一度作り上げたブランドを放置しておくとブランド力が弱くなってしまいます。ブランドのコモディティ化による弱体化や生活者の環境の変化などさまざま外的要因によるものもあります。ブランディングが成功した後もPDCAを回し、最適な状態にチューニングする必要があります。
ブランドデザインは、ブランディングに関わるデザインのすべてということを説明させていただきました。
戦略などのいわゆる上流工程は重要なのですが、生活者が実際にブランドに接する「ビジュアルデザイン」も私たちは力を入れています。
戦略に基づき、生活者の心理変容を考えた上で、競合他社に負けない「ブランド価値」を見つけ出したとしても、ビジュアライズで失敗すれば生活者に見向きもされません。まず生活者へのファーストアプローチであるビジュアライズがブランドには重要だということを覚えておいてください。今回は「ブランドデザインとは」を説明しました。みなさんがブランディングをする際のご参考になれば嬉しいです。
